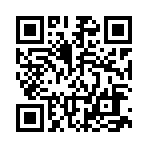2012年06月20日
56-2 ぐんまフランス祭=もんじゃ焼きのルーツ2
Bonjour!
それでは早速前回の続き、いよいよ核心です。

赤堀歴史民俗資料館内蚕産の様子
群馬は養蚕が盛んであったことで分かるように土地は痩せ、
米を含め農作物があまり育たず、しかしうどん粉(中力粉)やそば粉は多く取れ、
うどんやそばをよく食べたことから、
この「クレープ」を作ることは可能だったと思われます。

黒小麦のクレープ
そして、実際この時代に鉄板をわざわざ作って食す、
それもおやつとして一般的だった食べ物が庶民の間にあったとは
当時の経済状況から考えても不自然です。
つまり富岡にいたフランス人にとっては、富岡製糸場の前には
横須賀造船所で精鉄技術を伝授していたことからも
彼らにとっては精度の高い鉄板を手に入れることは
まったく問題がなかったわけです。

土手なしもんじゃ2
それにもともと昭和の初めの駄菓子文化の「もんじゃ焼」は
今日のように沢山の具を入れて、土手を作って焼くようなものではなく、
殆ど何も具として入れることはなく、薄く薄く焼いて食べたものです。
ですからある意味クレープを焼くための鉄板をわざわざ用意したと考えられ、
そしてそこでクレープを焼いてみせ、
焼きあがったものを
「食べなさい、食べなさい Mangez!Mangez!」と・・・。
つまりフランス語で 「モンジェ!モンジェ!」
これを聞いた当時の人たちはフランス語の意味は分からないので
これを「モンジェ」という食べ物だと理解したならば、
まさしくこれは「モンジェ焼き」つまり「もんじゃ焼き」に他ならないのです。
「もんじゃ焼き」は群馬県東部に多くあるといわれていますが、
「もんじゃ」は群馬県全域に存在していて、
群馬県中東部の伊勢崎や桐生は絹織物の産地、
中部の前橋などは養蚕や絹貿易で栄えたので、
群馬県西部に位置する「富岡製糸場」は絹織物工場であったことからも、
養蚕や絹に関係する場所に関係者から関係者に伝えられて
庶民でも作れる食材だったことから次第に食されるようになった
と考えるのが理屈に合っていると考えられます。

土手なしもんじゃ3
食べ方や焼き方は時代性や地域事情によって変化することは当然のことなので、
それに関してはそれほど重要ではないような気がします。
それでは何故、埼玉や東京下町特に浅草に「もんじゃ焼き」があるかというと、
江戸時代から旧中山道(国道17号&18号)を通ってたどり着くのが
まさに東京下町であり、
中仙道を通って江戸に上ったところに上屋敷があったのが
上州(群馬)や越後(新潟)です。
最近ではスカイツリーが出来たおかげで
これまで東武伊勢崎線と群馬の伊勢崎市まで結ぶ線が
東武スカイツリーラインとなり、伊勢崎という名称が消され
名称が変更されましたが、

昔の東武伊勢崎線
旧国鉄(JR)では、以前は日本がフランスと絹貿易のために
前橋から横浜まで鉄道を敷いて横浜港から絹製品を輸出した歴史があるように
以前は、東武スカイツリーラインは浅草から前橋までつながっていて、
かなり東京下町とは歴史的な関係が深いのです。

浅草寺の雷門・左右には雷神、風神が
それに実際、「かかあ殿下と空っ風」「雷の産地」
浅草の「雷門」には雷神、風神があり群馬の象徴と一緒と
いうのが不思議であり、
上州気質と江戸っ子気質はまったく同じ!!
「雷おこしは古くからの小麦の産地である
群馬のポンポン菓子を飴で固めたもので、
群馬県人が浅草で販売したのがルーツ」

浅草の雷おこし
現在一般的にルーツと名乗りを上げている東京下町の某地は
埋め立て地であり、もんじゃ発祥といわれる時代には、
その地はまだ存在していなかったようです。
勿論、もんじゃを普及させた功績は素晴らしいことだと思いますが・・・

土手なしもんじゃ4
関西方面のモダン焼きも、西洋のガレットのような
モダンな食べ物ということだったり、
広島のお好み焼きもクレープのように薄く伸ばして
そこに様々な食材を乗せ(折り込んで)完成させるのは
使用する食材が比較的似ていたりするので
ブルターニュガレットがルーツなのかもしれません。
こちらは想像ですが・・・。
現在の土手を作って焼くもんじゃは、商品単価を上げて
おやつとしてではなく、お好み焼きのように食事として成立するように
考えられた、商業ベースのもんじゃであり
歴史はそれをちゃんと証明しているので今のもんじゃの姿は
ルーツとは関係ないのだと思います。
でもガレットももんじゃ焼もモダン焼き(お好み)も広島風も
どれもそれぞれとても美味しい
「粉もの文化の象徴」
ということには異論はまったくないのですが・・・。
それと、最初の方でちょっとお伝えした「お好み焼き もんじゃ KANSAI」
ですが、KANSAIという社名ですが、
実は群馬の会社なんです。
群馬、埼玉、東京銀座に18店舗を展開する会社で日々進化を続けています。
ちょっと桐生の「築地銀だこ」や前橋の「サッポロ一番」のような
ネーミングの仕方ですよね。
お好み焼き もんじゃ KANSAI
本社:〒372-0055 群馬県伊勢崎市曲輪町29番地2-1
TEL 0270-23-4774 FAX 0270-23-4546
URL http://www.collabo-kansai.com/
それでは早速前回の続き、いよいよ核心です。

赤堀歴史民俗資料館内蚕産の様子
群馬は養蚕が盛んであったことで分かるように土地は痩せ、
米を含め農作物があまり育たず、しかしうどん粉(中力粉)やそば粉は多く取れ、
うどんやそばをよく食べたことから、
この「クレープ」を作ることは可能だったと思われます。

黒小麦のクレープ
そして、実際この時代に鉄板をわざわざ作って食す、
それもおやつとして一般的だった食べ物が庶民の間にあったとは
当時の経済状況から考えても不自然です。
つまり富岡にいたフランス人にとっては、富岡製糸場の前には
横須賀造船所で精鉄技術を伝授していたことからも
彼らにとっては精度の高い鉄板を手に入れることは
まったく問題がなかったわけです。

土手なしもんじゃ2
それにもともと昭和の初めの駄菓子文化の「もんじゃ焼」は
今日のように沢山の具を入れて、土手を作って焼くようなものではなく、
殆ど何も具として入れることはなく、薄く薄く焼いて食べたものです。
ですからある意味クレープを焼くための鉄板をわざわざ用意したと考えられ、
そしてそこでクレープを焼いてみせ、
焼きあがったものを
「食べなさい、食べなさい Mangez!Mangez!」と・・・。
つまりフランス語で 「モンジェ!モンジェ!」
これを聞いた当時の人たちはフランス語の意味は分からないので
これを「モンジェ」という食べ物だと理解したならば、
まさしくこれは「モンジェ焼き」つまり「もんじゃ焼き」に他ならないのです。
「もんじゃ焼き」は群馬県東部に多くあるといわれていますが、
「もんじゃ」は群馬県全域に存在していて、
群馬県中東部の伊勢崎や桐生は絹織物の産地、
中部の前橋などは養蚕や絹貿易で栄えたので、
群馬県西部に位置する「富岡製糸場」は絹織物工場であったことからも、
養蚕や絹に関係する場所に関係者から関係者に伝えられて
庶民でも作れる食材だったことから次第に食されるようになった
と考えるのが理屈に合っていると考えられます。

土手なしもんじゃ3
食べ方や焼き方は時代性や地域事情によって変化することは当然のことなので、
それに関してはそれほど重要ではないような気がします。
それでは何故、埼玉や東京下町特に浅草に「もんじゃ焼き」があるかというと、
江戸時代から旧中山道(国道17号&18号)を通ってたどり着くのが
まさに東京下町であり、
中仙道を通って江戸に上ったところに上屋敷があったのが
上州(群馬)や越後(新潟)です。
最近ではスカイツリーが出来たおかげで
これまで東武伊勢崎線と群馬の伊勢崎市まで結ぶ線が
東武スカイツリーラインとなり、伊勢崎という名称が消され
名称が変更されましたが、

昔の東武伊勢崎線
旧国鉄(JR)では、以前は日本がフランスと絹貿易のために
前橋から横浜まで鉄道を敷いて横浜港から絹製品を輸出した歴史があるように
以前は、東武スカイツリーラインは浅草から前橋までつながっていて、
かなり東京下町とは歴史的な関係が深いのです。

浅草寺の雷門・左右には雷神、風神が
それに実際、「かかあ殿下と空っ風」「雷の産地」
浅草の「雷門」には雷神、風神があり群馬の象徴と一緒と
いうのが不思議であり、
上州気質と江戸っ子気質はまったく同じ!!
「雷おこしは古くからの小麦の産地である
群馬のポンポン菓子を飴で固めたもので、
群馬県人が浅草で販売したのがルーツ」

浅草の雷おこし
現在一般的にルーツと名乗りを上げている東京下町の某地は
埋め立て地であり、もんじゃ発祥といわれる時代には、
その地はまだ存在していなかったようです。
勿論、もんじゃを普及させた功績は素晴らしいことだと思いますが・・・

土手なしもんじゃ4
関西方面のモダン焼きも、西洋のガレットのような
モダンな食べ物ということだったり、
広島のお好み焼きもクレープのように薄く伸ばして
そこに様々な食材を乗せ(折り込んで)完成させるのは
使用する食材が比較的似ていたりするので
ブルターニュガレットがルーツなのかもしれません。
こちらは想像ですが・・・。
現在の土手を作って焼くもんじゃは、商品単価を上げて
おやつとしてではなく、お好み焼きのように食事として成立するように
考えられた、商業ベースのもんじゃであり
歴史はそれをちゃんと証明しているので今のもんじゃの姿は
ルーツとは関係ないのだと思います。
でもガレットももんじゃ焼もモダン焼き(お好み)も広島風も
どれもそれぞれとても美味しい
「粉もの文化の象徴」
ということには異論はまったくないのですが・・・。
それと、最初の方でちょっとお伝えした「お好み焼き もんじゃ KANSAI」
ですが、KANSAIという社名ですが、
実は群馬の会社なんです。
群馬、埼玉、東京銀座に18店舗を展開する会社で日々進化を続けています。
ちょっと桐生の「築地銀だこ」や前橋の「サッポロ一番」のような
ネーミングの仕方ですよね。
お好み焼き もんじゃ KANSAI
本社:〒372-0055 群馬県伊勢崎市曲輪町29番地2-1
TEL 0270-23-4774 FAX 0270-23-4546
URL http://www.collabo-kansai.com/
Posted by フランスさん at 06:00│Comments(0)
│ぐんまフランス祭り
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。